| so | ||||||||
|
|
||||||||
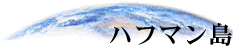
![]()

国境線・都市の位置は5thのブリーフィング。赤実線は鉄道、灰実線は道路をおおまかに表す。バリンデン西方沖の島に関する情報は特になし。縮尺は面積をもとに算出している。世界地図上での表示は[世界情勢 ]または[ google maps ]でどうぞ。
FMO公式サイトなどで使用された地図では山岳地・平地などの地形を読み取ることは難しいため、SFC版1stの攻略本を下敷きとしている。また、(地図投影法によるもかもしれないが)島の形状も1995年当時とFMOサイトとFMOゲーム中(Scramble Board上)でそれぞれ異なる。
| 面積 | 79,215平方km(参考:北海道78,420平方km) O.C.U.領:45,265平方km U.S.N.領:33,950平方km |
|---|---|
| 人口 | 455万人(定住者人口) O.C.U.領:182.6万人 U.S.N.領:272.4万人 |
| 人口密度 | 57人/平方km |
| 通貨単位 | H$(ハフマンドル) |
| 公用語 | 英語 (O.C.U.領内では日本語と中国語、U.S.N.領内ではスペイン語とフランス語が通用する地域もある) |
| 米生産量 | 48.2万トン |
| 野菜生産量 | 77.8万トン |
| 乳牛 | 33.5万頭 |
| 肉用牛 | 87.2万頭 |
| 豚 | 48万頭 |
| 漁獲量 | 93.2万トン |
| 石油産出量 | 216.3千キロリットル |
| 天然ガス産出量 | 12億5820.3万立方m |
人口20万人の湾岸都市。内陸漁が主流であるハフマン島では珍しく、太平洋を中心とした遠洋漁業が活発に行なわれており、紛争前はO.C.U.諸国の貿易船を上回る数の漁船が見られた。また、サバンナ地帯の温暖な気候により、牛や豚などの酪農・畜産も盛んである。紛争後は、外洋に面する港が、本土からの補給物資の到着地点として活気にあふれている。
海岸線まで山地が広がった地域にある中規模の都市。人口は10万人程度、住人は鉄道や高速道路を使って隣接都市へ通勤。沿岸西の50キロ沖にある無人島の調査目的で紛争直前に空港が建設されたが、紛争中はO.C.U.軍の航空部隊が待機する軍事拠点のひとつとなった。
島の南西部に広がる密林地帯は大部分が未開発で、メナサはその未開発地帯の入口に当たる都市。紛争前にO.C.U.諸国の産業複合体で編成された開発団が、ハフマンハイウェイ4号線の建設と西ハフマン鉄道の延長に成功したが、移住者は少数。第2次ハフマン紛争では、U.S.N.軍が内陸湾を潜航し、この地域に上陸。紛争が本格化したといわれる。人口20万人。
人口90万を誇る中西部の大都市。人々の生活水準は島内でも高く、街の繁華街には高級ホテルや華やかなブティックなど商店が建ち並ぶ。国境線が近く、紛争前にはドル、Hドル、ギル、チップなど両陣営の紙幣が乱れ飛んだ。運河に映しだされる夜景の美しさは有名で、紛争中に他の都市が給水制限を厳守していたにもかかわらず、フリーダムはその命令を拒んでいたともいわれる。
人口30万人、O.C.U.領土随一の商業都市。地形条件が悪いながらも、ハイウェイと鉄道が通 過する流通の中継地点だったことで発展した。東に広がる砂漠地帯はハフマン島隆起の時点では海水湖だったが、後に乾燥し現在の砂漠地帯となった。第2次ハフマン紛争中、フリーダム市の陥落で人口が増加し、ラークバレー壊滅で再び交通・流通の要所となった。
メール川沿いに位置する地方都市。人口は5万人とハフマンで最も小環模だが、メール川からの豊富な水を利用した稲作と野菜栽培が盛んで、その生産性はかなり高い。タッカー山脈を越え、ソレイトヘ続くハフマンハイウェイ2号線沿道では、のどかな田園風景を眺める。紛争中、領土境界線付近ということもあり、激しい戦闘が繰り広げられた。
タッカー山脈の西部に位置する都市で人口50万人。周辺を複数のハイウェイが縦横に通っており、そこを通る旅行者相手の商売が主な産業となっている。総合ショッピングセンターチェ−ンであるパシフィックマーケットプレイスも進出している。また、北西のぺセタ同様に農業が盛んで、半ば観光地と化しているが牧場も数ケ所が経営されていたが、第2次ハフマン紛争勃発後、ハイウェイは軍事物資の輸送路として軍が使用。街は途端に活気を失った。
当初は観光地開発として入植が進んだハフマン島だが、北東部のタッカー山脈などの豊富な鉱物資源発見により、国を問わず多くの企業が競って工業プラントを建設した。ソレイト周辺には鉱物や天然ガスなどの抽出工場が集中し、瞬く間に一大工業地帯へと発展したが、第2次紛争後は活気も衰えた。ハフマンの自然破壊を憂う保護団体も登場、その一部が後に「ハフマンの魂」と名を変え、サカタ社に対するテロ活動を操り返した。
同じ商業都市であるO.C.U.のグレイロックと比較されることも多いが、林立する高層ビルの規模や60万人の人口、生み出される経済効果のいずれにおいてもファートモーナスが勝る。第2次紛争は、このフォートモーナスのO.C.U.進軍によって終結に至った。
紛争中はU.S.N.軍の補給地として利用された湾岸都市。120万人という、島内では最大の人口を誇る。第1次紛争終結時から、この地域へのサカタインダストリィの進出が目立ち始めた。恒平和調停機構軍の介入によって軍事需要が減少すると、大型トラックで各地を移動しながらキャンプを張って売買を続ける武器商人たちが現れた。
イーストハフマンラインの支線の終点となる海沿いの町。フォートモーナスへ通じる支線の建設で中継地、観光地?としての発展が期待されたが、紛争の影響で建設は中断。紛争後も建設再開はされず寂しい町となっている。
原油産出の可能性が持ち上がり砂漠を横断するルート上に建設された町。第2次紛争時に、U.S.N.軍の無差別攻撃により壊滅。確認されている生存者はモーリー・オドネルの1名のみ。町の崩壊後、オドネルは軍に恨みを持ち、進入する両国部隊に抗戦していた。無差別攻撃についての詳細は[第2次ハフマン紛争]参照。
フォートモーナスから100キロほど南下したところにある島。希少な海鳥の繁殖地として、PMOにより国際自然保護区域に指定され、人間の居住、戦闘行為が全面禁止されている。紛争以前は多くの観光客が見られた。また、極秘にサカタインダストリィの研究施設が建設されていたが、紛争後にハフマンの魂により爆破された。