
−祖国達の島−
・種別/書籍紹介
・広告主/フレデリック・ランカスター氏
・お問い合わせ/――――
|
 |

| ― 掲載項目一覧― |
| 序章 |
プロローグ |
第六章 |
私の居場所 |
|
空の青さ、風の声
妻の笑顔 |
|
時の流れが止まった時
記者の第六感?
魂が語るとき・・・。 |
| 第一章 |
人生のif |
第七章 |
最高の絆、キャニオン・クロウ |
|
自暴自棄になっていた時
ハフマン島への左遷
妻と娘との別れ |
|
ナタリー、離れる・・・?!
リュウジの想い
家族のケリは俺がつける! |
| 第二章 |
自分の旅・・・ |
第八章 |
誰も知らないロングリバース島 |
|
自分を探す旅
始まりは輸送機墜落
恋人と弟と探し人 |
|
輸送ヘリ
地下施設
バイオニューラル・デバイス |
| 第三章 |
傭兵部隊 |
第九章 |
罪と罰 |
|
渓谷の鴉
地獄の壁
その名はクリントン |
|
向かい合う兄弟
「平和の勲章」という名の悪魔
心を持つ兵器 |
| 第四章 |
罠 |
第十章 |
運命共同体 |
|
たった一人の戦い
メ−ル河国境
鷹の涙 |
|
再始動
永遠に、キャニオンクロウ |
| 第五章 |
仕組まれた終戦 |
終章 |
エピローグ |
|
最後の戦い
野戦病院
目の前の味方は仇?! |
|
家族 |
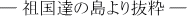
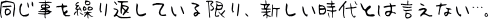
 私は、一流記者だと思っていた。周りの同僚達もそう思っていると信じていた。だが、現実は違っていた。軍と企業との癒着を暴露する記事を書いたために、こんな時代遅れの場所に左遷されたのである。 私は、一流記者だと思っていた。周りの同僚達もそう思っていると信じていた。だが、現実は違っていた。軍と企業との癒着を暴露する記事を書いたために、こんな時代遅れの場所に左遷されたのである。
この2090年代の人間は平和ボケしていると言ってもいい。好きこのんでドンパチやるなんて狂った人だけだ。しかし、ここだけは違う。二大勢力の未来をかけた戦いが続いている。最初、私は自分の運命を呪った。こんな辺境に飛ばされてと・・・。しかし、キャニオンクロウに出会って全てが変わったと言えるだろう。
恥ずかしながら、今は妻と別居中なのだ。「私と仕事のどちらが大切なの?」なんて古風な言われ方をされた。私は仕事を頑張ることで妻が喜んでくれると思っていた・・・・。
「温故知新――――古きを訪ね新しきを知る」夫婦間にも言えるかも知れない。大切なものが遠くに行ってしまってから、大事なものが近くから離れてから気づいてしまったのだ。キャニオンクロウの従軍を私自身が願い出たとはいえ、戦闘中に逃げ出そうと何度も思った。しかし、逃げ出さなかったのは「記者魂」「妻との別居」・・・。ここで逃げるのは簡単だが、それは自分から逃げるものではないのか?と自問自答を繰り返した。そして今では、この傭兵部隊に志願従軍して幸運だと思っている。
 [鷹の涙]作戦・・・、OCUがフォートモーナス攻略をかけた最大の作戦である。私も新聞記者として、そして部隊員としてキャニオンクロウと共に命令を受けた戦地へと赴いて行く。そこはモーガン高地にある巨大な要塞だった。 [鷹の涙]作戦・・・、OCUがフォートモーナス攻略をかけた最大の作戦である。私も新聞記者として、そして部隊員としてキャニオンクロウと共に命令を受けた戦地へと赴いて行く。そこはモーガン高地にある巨大な要塞だった。
私には、守らなければならないものもあるし、こんな所で死ぬつもりも毛頭ない。なにより死んでしまっては娘に合わせる顔がない。しかし、後ろから歩み寄ってくる『死』をこれほど感じたことがなかった。
目の前には、モーガン要塞が不気味に聳え立っている。ランド・デストロイヤーの別名を持ち、文字通り全てのものを破壊してきた。そして、巨大な口を開けた鉄の塊がこちらを見ているのである。通称アポロ、アテナ、ゼウスと呼ばれる巨大砲塔は射程が10キロに達し、その破壊力は想像を絶する。ヴァンツァーと言えど、一発が命取りになりかねない。足が竦み始めた時ハンスが私の心を代弁したのである。
「この要塞をこれだけの人数で倒せっての?!」
その言葉にサカタが自信有り気に返す。
「これだけの人数だから、有利なのさ。大きいものは、小さい標的を狙いにくい。散開して的を絞らせず懐に入っていく。接近してしまえば、こちらが一方的に攻撃できる。勝機はある!」
さすがは、サカタである。動じること無く、的確に状況判断している。そして、ロイドの叫びと共に最大の戦いの火蓋が切って落とされた。
 もちろん、一般者の上陸は基本的に認められていないのだから私もロングリバース島は初めて。私は、輸送ヘリからロングリバース島を眺めながらある一つの決意を固めていた。この島(ロングリバース島も含めて)で起こった全ての真実を世界に公表すると・・・。 もちろん、一般者の上陸は基本的に認められていないのだから私もロングリバース島は初めて。私は、輸送ヘリからロングリバース島を眺めながらある一つの決意を固めていた。この島(ロングリバース島も含めて)で起こった全ての真実を世界に公表すると・・・。
自慢ではないが、私が勤務しているトキオ・タイムス社は新聞紙販売部数世界一なのである。なら簡単に世界に公表できると思うかもしれない。しかし、このデジタル時代において新聞は時代遅れなのである。 みんなネットやら携帯電話で情報を集めているのだから。私は、新聞はもちろんのことテレビ、雑誌、政府・民間機関など出来うる限りのことをしたいと思っている。もちろん、ライバル会社のデイリー・フリーダムやJBNN、デイリー・キャンベラ・ネットワークなどの新聞社にも情報を渡すつもりでいる。こんなことをしたらクビは間違いないだろうが、今更どうでもいいことだ。死語だと言われるかもしれないが「真実はいつも一つしかない。」これが私の記者としての持論である。この言葉を失くさない限り私は、活動を続けるだろう。
最後に言いますが、私はあの言葉を信じ続けていくことが出来たから自分を見つけることが出来たかもしれません。彼らの願いが届くことを私は祈り続ける。
|
 |







